今日は考えさせられる一幕といいますか、自分もそんな考えだったな・・・。と思う瞬間がありました。本年度は大エージェント時代と言われてスタートする中、日々の作業ベースの取り組みはAIに代替されることが目立ってきました。自身もこれまで着手していなかったAPI連携による一連の作業を流しで行える仕組みの構築や簡単なSaaSで提供されてきた仕組みはv0先輩の力を借りながら自社で賄える体制を整えることが増えてきました。
開発の人間も運よく組織に入ったため、クラウド化・アプリ化についても不安なく運営し始めた頃合いとなっています。巷で話題にある通り新人として社会に属する人間にとっては過酷な時代になり始めたことを感じる今日この頃といったところでしょうか。
エージェント化を強権的に推進している人がいる中でAIを触り始めたころの感情が出てきたので、こうしてキーボードをたたいてるわけですが、「AIに人の仕事が取って代わられる」と最初の頃は言われてきました。まぁ、今となっては一定事実と認めざるを得ないでしょう。とはいうものの感情面を排除して組織づくりないし、選ばれる商品・サービスは生まれないことも事実です。AI触りたてのころはまるで魔法使いになったような、異世界転生したような無双感はあるものの、その先は二分すると考えています。
1つ目はそのまま販管費を下げて、商品・サービスに対する時間を割く組織作りを進める。私生活も含めて効率・システム化を推奨するタイプと考えます。2つ目は結局村社会の感覚に戻る人です。私の現在は後者となりましたが、もうじき3年目を迎えるわけですが、ずっと考え続けて今の感覚に至ります。
AIを一般の人が使えるようになった2023年11月。当初はgpt-3でしたから万能型ではありませんでしたね。マルチモーダルなんてもってのほかで、上位者でも苦戦する時だったと思い返します。そこから現在はエージェント化が一般化し、プロンプターは消え去り、バイブコーディング勢が大手を中心に中小にも根を下ろし始めたころなんでしょうか。今月も新たなブラウザにエージェント型サービスの強化版も登場し、いよいよ効率化を迫られるときが近づいてきたなと感じています。
1つ目は確かに大事な考えで、DX推進に補助金が出るほどに少子高齢化による推進は間違いなく起きています。実際に、ほとんどの業務に対して組み込んでいるのですが、従来の自分よりはるかに多くのタスクをこなし、不要な接触は避けて自分時間を確保できたことに対する恩恵を計り知れなく受け取ってきました。しかしながら、2つ目の考えに至った理由としては「AIの進む先に人はいない」という感覚を持ったことが大きな要因だと考えています。
実際、自動運転技術が普及しタクシーなどは無人で走ってますし、工場の従業員はロボットで人はほんの少し接触する程度という現場も存在します。その方が効率的ですし、自身がある程度自由に使える富を持っていれば同じ選択をするでしょう。でもそこに人はいません。大規模なドーム何個分みたいな工場であっても誰もいないのです。
じゃあ、大規模な視点で世界の経済はどうなっているのか?中小であくせく働く人たちはなぜいるのか?という視点に立った時。理論ではない世界線が存在している事実を受け止める必要性を感じました。等価交換性でボランタリー経済の世界とでも言うんですかね。この感情・感覚・魂の世界線は根強くあり、この先も区画が整備されて超監視社会みたいな街が作られない限りは残り続けると今は考えています。
AIがいたとしても人はあり続ける。まぁ至極当たり前のことを言ってますが、一度AI漬けの世界に入ったら新鮮な感覚で受け止めることができました。先の事例で推進する中で摩擦や抵抗の場面があり、自身も一定の抵抗感を示したわけですが、全然違う感覚で抵抗感を示していると考えています。別に仕事が取られるからとかではなく、感情などを置き去りにしたサービスが生まれようとしていることに自分は抵抗したんですね。
確かに1分待てば希望するものが出るのであればありがたいです。しかし、それを他社に頼むことに何の価値があるのでしょうか?Xを見れば30秒で理解できることに10万も20万も払うなど情弱と言わざるを得ないでしょう。価値なき技術の安売りをしても双方に得はなく、むしろロジックがばれた時にクレームの嵐になるのは間違いありません。この感情や感覚を置き去りにすることに対する怖さのないAI利用が組織破壊を生んでる一端でもあるのではと考えます
よく、AIの講習をする際は「あなたにとって人ですか?機械ですか?」という質問をしています。これにはいろんな理由が含まれているのですが、マネジメント能力やリーダー能力といった座学だけでは培えない力を持たないと正しく扱えないからという理由が一つあります。IQだけで言えば自分など足元の小指の先端の細胞のナノ分子レベルで足元にも及ばない存在です。しかしながら、うまく感情をコントロールするすべなくタスクを任せたところで、思った成果がでない経験をgpt-3時代にしています。
エージェント化した今。スマートフォンを持ったころの感覚同様に万能感があり、軽いプロンプトで想定外のところまで対応してくれます。最近になって様々な論文が出始めて、脳への影響や逆に非効率化するなどの資料も出始めましたが、感情・感覚的側面の体系的というかお墨付きのある情報は乏しいように感じます。自身は中小零細のジャンルに入る組織におるわけですが、統計通り16%くらいの浸透率で44%くらいの個人利用率といった印象を持っています。
しかし、実務に落とし込んでパートナー的に活用している人間に制限したら0.05%とかでしょう。組織で強制的に利用させる風土を作るのも大事ですが、中小の人間などは学歴も知れた人々ですから、トップダウンの風が効かない組織もあるでしょう。伝播役の人間を育成するのも大変でし、利用することが息することと同格に持っていくのは至難の業です。そうなるとエージェント化による強制執行になってくるわけですが、そうなったときに焼き払われるくらいの衝撃波が生まれると感じています。
衝撃波は心理的に波及してゆらぎが起こるわけですね。この感覚を理解せずに推し進めた先には言われたことを粛々とやるだけの組織となっている気がしているのです。何か統計結果が出たわけでもないので、あくまでも感覚的にそう思うだけのことなので、得られるのは共感くらいでしょうか。
それを確信している理由としては海外のどんな人を重宝するか?という話から結論づけています。仕事ができずとも居てるだけで回りが笑顔になる人や圧倒的なホスピタリティで頼りにされる存在。カリスマ性を持った方や狡猾な動きで円滑な立ち回りをする人などなど。自身を軸とした価値提供で組織パワーが高まる人材に注目しているという話を聞いて納得しました。資本主義が成熟から完熟になったころにはAIの進化もあってより顕著になっていくと現在は考えています。
よく管理職は不要になる話を聞くのですが、代取も同様のはずなのです。しかし、代表取締役がAIの法人はなぜかないんですね。党首がってのは最近でましたが、AIを是とするならば組織の在り方も是としなければ納得がいかないにも関わらず、そこは人が主役みたいな顔をするわけです。しかし、投資は機械・AI・DXという大きな矛盾が生まれていると感覚的に思っています。
完熟化してしまったら、螺旋式の進化をしていくことを歴史の観点から踏まえるとボランタリーと融合していく可能性があるわけですが、そうなったら人が主体の組織で、その組織同士がつながっていって分散されたコミュニティーに刺さっていく。村同士・隣同士がつながっていく江戸時代・室町時代みたいな営みが主体になっていく気がしています。もちろん丸々村みたいになるわけでなく、テクノロジーがあり、人が居て、流れが作られている状態であることが前提です。
信用スコアなどもあるかもですが、数値・理論では測れない魂同士の共鳴みたいなものを感じ取れる人たちで資本の共有や繁栄が進んでいくのではないか?と今は考えています。第6感や第7感を研ぎ澄ませ!みたいな話もありますが、我々は昔からそんな感覚を当たり前に持っている気がしています。AIの普及は数をより確保するための作業者ではなく、自身の相棒として人と接するための技術やコミュニティ形成のために使える時間を確保できるように、任せるところは任せつつ、何をやるべきかを見極めて、少し長い目で考えた行動をとるべきかなって最近は思っている次第です。
長くなりましたが去年の自分を見てるような感覚を体感したので、今現時点の考えをまとめてみました。Xでぜひ感想を聞かせてください。


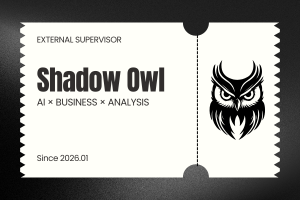
コメント